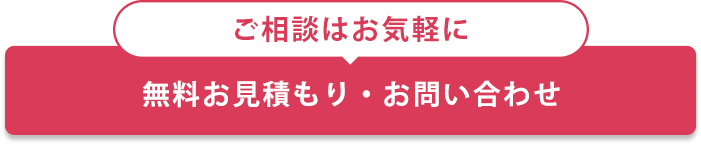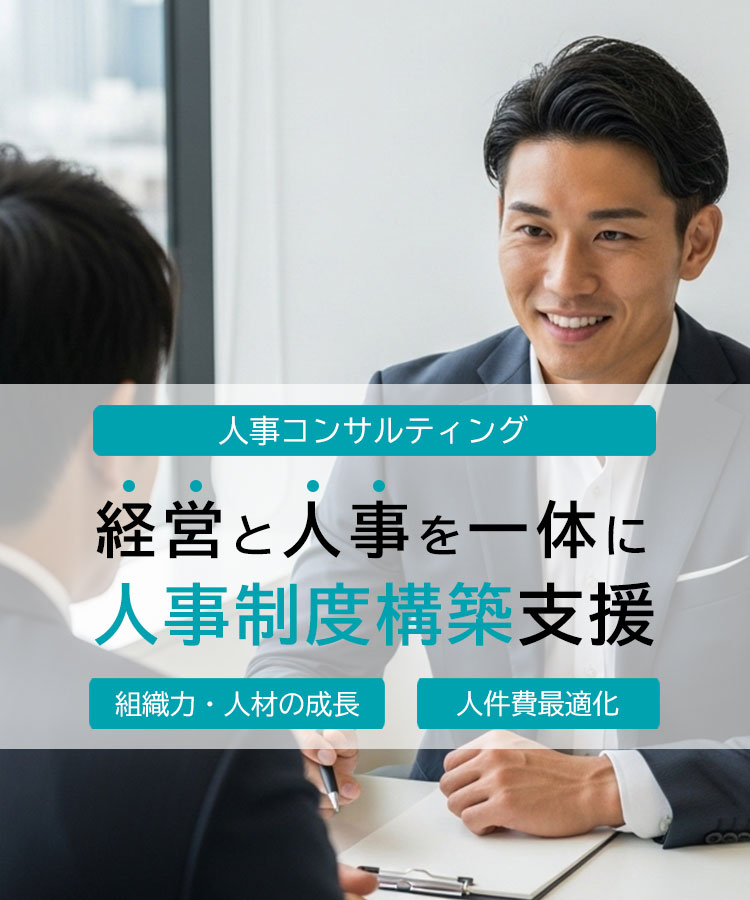「人事制度構築」が企業を変える!
人材の質と組織の力が企業価値を決定づける現在、人事制度は単なる評価・処遇の枠組みに留まりません。
経営理念を現場に浸透させ、組織全体を持続的な成長軌道に乗せるための“経営インフラ”として、制度の再設計が求められています。
![]() 現場と経営の橋渡し
現場と経営の橋渡し
現場と経営層の視点のズレを埋め、社員が自らの成長を会社と重ねて描ける制度設計を実現。
![]() 制度の仕組み強化
制度の仕組み強化
「役割と評価」「職務基準」を明文化し、処遇と連動させることで組織力と生産性を高めます。
2つの成果を同時に実現する制度構築
組織力・人材の成長
育成方針と評価指標を整備し、持続的な人材開発を実現。
人件費最適化
評価と処遇をつなぎ、コストコントロールを実現。
この両輪が回ることで、人事制度は“経営システム”として機能します。
なぜ、人事制度はプロに任せるべきなのか?
– 組織を変える本質は「制度」にある –
経営者の多くが、「社員が主体的に動かない」「管理職が責任を果たさない」「組織がなかなか育たない」といった悩みを抱えています。
こうした課題の根本には、経営者と社員の間にある“視野と視点”のギャップが横たわっています。
このギャップを埋め、組織全体を一段階引き上げるためには、人事制度の整備が欠かせません。社員が自らの将来像を会社の成長と重ね合わせられるようなビジョンの提示、そして会社が期待する役割・責任を明確にし、それを処遇と結びつける仕組みが求められます。

私たちは、人事を経営の手段として機能させる「経営人事システム」の構築を支援しています。制度設計は単なるルール作りではありません。人材の成長と企業の持続的成長を同時に実現させる、戦略的な経営ツールです。だからこそ、現場に入り込み、経営目線で制度を設計できる人事のプロフェッショナルの力が必要なのです。
人事コンサルティング「サポートのステップ」
企業の課題に向き合い、最善策をご提案
Step 1
現状分析・基本方針
人事制度構築の第一のステップでは、現状分析を行い、問題点を整理して今後の人事制度の基本方針を明確にします。
この作業をきちんと実施しないと、社内で制度改定を行ってもうまく行かない大きな要因となり、いつまでたっても新制度を構築できなかったり、何度案を作成しても幹部のコンセンサスが取れないといった状況が発生してしまいます。
最初の段階で現状認識と方向付けをしっかり行うことにより、効率的な設計方法で自社にとって適切な人事制度を構築することが可能になります。
Step 2
等級制度の設計
等級制度の設計では、まず会社が期待する具体的な人材像を明確化し、それを基盤に職務・役割レベルに応じた等級を設定します。
理念と制度が乖離すると形骸化しやすいため、経営者の想いを反映させ一貫性ある仕組みとすることが重要です。
人材像は評価や処遇、育成の根拠となり、理念浸透や組織風土の形成にも寄与します。また、役職と等級を対応させ、昇進と昇格、降職と降格を明確化することで年功的な運用を防ぎ、人事と経営の整合性を保ちます。
Step 3
賃金制度の設計
賃金制度は企業経営の根幹であり、自社の賃金支払能力や同業他社水準を踏まえたモデル賃金を描くことから始めます。基本給の体系を整備するとともに、役職手当や地域手当など諸手当を抜本的に見直し、制度の公平性と透明性を確保します。
さらに、移行シミュレーションを通じて新旧制度間の調整を行い、社員への影響を最小限に抑えます。賃金制度の設計は、持続可能な人件費運営と社員のモチベーション維持を両立させるための重要なステップです。
そのためには、等級や役割に応じた基本給体系を設計し、昇給のルールやキャリアステップとの連動を明確にすることが不可欠です。賃金制度を人事評価制度や等級制度と一体的に構築することで、処遇の一貫性と納得感を高められます。
また、制度改定の目的や内容を丁寧に社員へ説明し、理解と受容を促すことも重要です。こうしたプロセスを経て設計された賃金制度は、経営戦略と人材活用をつなぐ基盤となり、組織の持続的な成長を支える力となります。
Step 4
賞与・退職金制度の設計
賞与制度の設計では、まず夏季・冬季賞与の総原資を、その期の業績や将来見通しを踏まえて経営者や経営陣が決定します。
原資は部門別や個人別に配分されるのが一般的で、個人別賞与は基礎額に人事評価格差を掛けて算出する方法が合理的です。基礎額は基本給と役職手当の合計、基本給のみ、あるいは等級ごとの一律額などで設定できます。
一方、退職金制度は賃金や賞与、福利厚生と区別して「功労報奨」として設計することが望ましく、特に基本給を大幅に改定する場合はポイント制退職金が適しています。ポイント制では「勤続」「等級」「役職」の各ポイントを組み合わせ、モデル退職金をもとに功労と報酬のバランスを検討し調整します。これにより、制度全体の公平性と透明性を確保しつつ、従業員の貢献度に応じた報酬を実現できます。
Step 5
人事評価制度の設計
人事制度の中で特に重要なのが人事評価制度です。制度全体の基本理念は職務や役割を基準としていますが、それだけではなく、自社にとって欠かせない行動規範や価値観も存在します。
人事評価制度は、職務・役割を軸としつつ、企業理念を浸透させるために必要な評価項目を丁寧に検討して設計することに意義があります。そのため、人事評価表に「これが絶対の形式」というものはありません。
弊社では、企業の規模や業種、組織風土を十分に理解したうえで、組織と人材が最大限に活性化する評価システムを設計・提案しています。
Step 6
新人事賃金制度の運用開始準備
全ての人事制度とその運用方法をマニュアルとしてまとめることで、経営層や管理職から社員へ統一した内容で説明が可能になります。
社員説明会は、人事制度改定の目的や内容を全社員に理解してもらう重要な場であり、具体的な変更点を明確に伝えることで、社員の納得感を高め、疑問や不安を解消し、制度への信頼を築くことができます。
弊社では、「新人事制度の説明資料作成」「説明会での説明」「質疑応答対応」を支援し、円滑な導入と業務推進をサポートします。
また、運用段階で人事評価制度が機能しなくなるケースの多くは、被評価者に適正な評価が行われず、いわゆるイメージ評価に起因することが散見されます。そのため、運用開始前に評価者全員が制度を正しく理解し、評価基準の認識を共有するとともに、面談に関する正しい知識を習得することが極めて重要です。
ご利用実績

人事制度改定 一般企業事例

会社概要
| 業種 | 店舗系販売業 |
|---|---|
| 従業員数 | 400名 |
| 売上 | 150億円 |
制度改定の背景
| 背景 | 旧制度から20年経過し、微調整では限界に達したため全面改定。モチベーション向上と今後10年間の安定運用を目指す。 |
|---|
新制度の主な改定ポイント
| 1. 等級設計 | 等級・呼称・役割の関係を明確化。等級フレームを設計。 |
|---|---|
| 2. 初任給 | 世間相場並みに引き上げ。 |
| 3. 基本給体系 | 複雑だった構成(年齢給・資格給・本人給)を一本化。 |
| 4. 賃金表形式 | ゾーン型賃金表を新設。範囲職務給を採用。 |
| 5. 管理職の逆転現象是正 | 等級手当・役割手当で賃金バランスを是正。 |
| 6. モデル賃金 | 年齢別・役職別・等級別に処遇を可視化。 |
| 7. 諸手当の見直し | 整合性を欠いた手当を総合的に再整理。 |
| 8. 退職金制度 | 年功型→貢献度反映型ポイント制へ移行。 |
等級制度
| 等級数 | 6等級 |
|---|---|
| 内容 | 各等級の定義・役割を明文化。店舗系・本部系の序列を整理。年数モデルで昇格速度を可視化。 |
賃金体系
| 基本給 | 3要素を一本化し実力主義化。 |
|---|---|
| 管理職手当 |
等級手当:例)6等級7万円、5等級6万円など 役付手当:例)部長6万円、次長4万円など |
賃金表
| 特徴 | モデル賃金を22~60歳で明示、ゾーン型賃金表で役割連動の水準を設定。 |
|---|
人事評価制度
| 制度 | 目標管理型評価制度(今回は改定対象外) |
|---|
制度導入の効果
| 処遇改善 | 組合の要望を全て取り込み、全面賛成を得た。 |
|---|---|
| 原資投入 | 約3,000万円を確保し、給与改善を実施。 |
| 組織風土 | 管理職のモチベーション向上、チームワーク重視へ風土転換。 |

障害者支援施設における事例

法人概要
| 法人名 | 社会福祉法人A |
|---|---|
| 創立 | 20年超 |
| 運営事業 | 生活介護事業所2拠点、グループホーム4棟 |
| 職員数 | 常勤18名 |
| 特徴 | 公務員準拠型の年功序列的給与制度を長年運用 |
制度改定前の課題
| 経営状況 | 比較的良好で安定している |
|---|---|
| 主な課題 |
年功序列によるモチベーション低下 若手職員の離職率が高い キャリアパス不在 次期リーダー層が育っていない |
具体的な改定内容
| (イ)等級フレームの整備 | これまで等級制度がなかったため、新たに6等級の等級フレームを策定。 |
|---|---|
| (ロ)手当体系の見直し | 属人的手当を抑制、役職・資格手当に配分。定率手当を定額に変更し人件費増を抑制。 |
| (ハ)給与表の策定 | 基本給ピッチを4,000円で設定。年齢給を廃止し、職能給に一本化。昇給は習熟昇給と昇格昇給の比率を2:1と設定。 |
| (ニ)人事考課制度導入 | リーダー層を含むプロジェクトチームで制度を設計。法人が求める職員像を反映し、貢献度に応じた処遇へ移行。 |
改定後の成果
| 等級制度の効果 | 階層ごとの役割意識が高まり、組織力向上。 |
|---|---|
| 考課制度の効果 | リーダーの育成意識向上、若手の定着率改善。 |
今後の展望
| 展望 | 若手職員を次期リーダーに育て、将来の事業展開に活用。 |
|---|
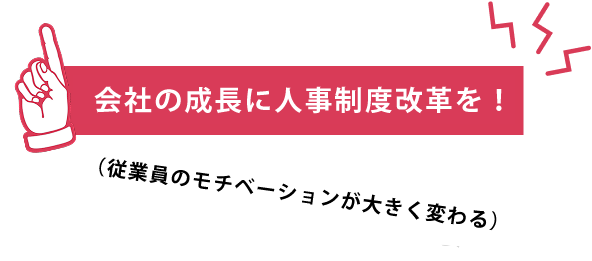
「組織の停滞は、制度が原因である」
経営と現場のズレを埋めるには、制度の再構築が不可欠。
「評価制度の整備が、人を動かす」
仕組みが明確になった瞬間、社員の行動が変わり始める。
「管理職は「制度」で育てるもの」
責任と裁量を与えることで、管理職は組織を動かす推進力へと変わる。
「人事制度は経営そのものである」
企業の成長を下支えする経営インフラになる。